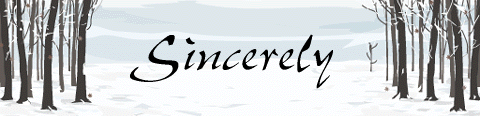
.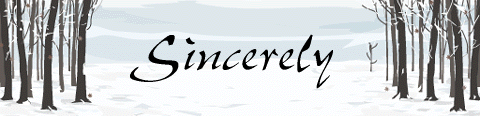
マリアは一人ぼっちだった。
優しかった両親は流刑地での劣悪な生活に耐えられず、病に倒れそのまま帰らぬ人になった。
そして両親を失った9歳の少女はある夜、流刑地を後にした。とにかく、この地から離れたい、それだけだった。親を亡くした少女が一人いなくなっても、さしたる問題にはならなかったらしい。大した追っ手にも合わず、マリアは脱出に成功した。しかし、それは死との戦いの始まりだった。
粗末な防寒服とわずかな携帯食料。それが今マリアの命をつないでいた。赤々と燃えるストーブも、暖かな湯気を立てるスープもここにはない。それでも9歳の少女は果てしなく広がる雪原をあてもなく歩くしかなかった。
わずかな食料が尽きてからは、雪でのどの渇きを癒し、時には木の皮も食べた。生きるためにとにかく進むしかなかった。しかし、それも長くは続かなかった。森の中でとうとうマリアは動けなくなった。
動けなくなったマリアの頭に肩に雪が降り積もる。しかし、それを払いのける力はもうマリアには残ってはいなかった。
(とうさま…かあさま……マリアも今そこに行きます…)
倒れた木にもたれかかるようにしてうずくまったまま、マリアはゆっくりと眠りに落ちていった。
ユーリーは小隊を率いて周辺の流刑地を巡って基地へと帰還するところだった。途中、ブリザードと遭遇、予定がかなり遅れてのことだった。隊員たちにも疲労の色は隠せない。
「よし、ここまでくればあと少しだ。ここらで小休止しよう。」
森の奥に入ったところでユーリーはそう言って、休める場所を探した。ふと、目の前にかなり大きい樹が倒れているのが目に入った。
「あの樹のところで少し休もう。」
重い足を引きずるようにしながら、さらに置くに倒れている樹に向かって歩いた。
「ユーリー、ちょっと来てくれ。」
先行していた隊員に呼ばれて駆け寄ったユーリーは驚いた。
「…先客がいたようだな。」
「これは…女の子だ。まだ息はあるな。…こんなに冷え切って…誰か毛布を。」
毛布が渡されると少女の身体をくるんだ。
「この子の親が近くにいないか探してみてくれ。」
小一時間あたりを探索したが、痕跡すら発見することはできなかった。
「とにかく、この子だけでも助けなければ、基地に戻るぞ。」
ユーリーの言葉に隊員は再び歩き始めた。
目を覚ますとマリアは暖かく明るい部屋の中にいた。
(これはどこ?…天国?)
しかし、その考えを否定するように身体の節々や、手足の指先が痛みを訴えた。
「…痛ッ……」
身体は痛みを訴えるが、とりあえず私は起きあがって、周りを見渡した。
崩落防止の木が組まれた洞窟の中であった。
「やあ、やっと気がついたな。」
一人の若い男が立っていた。
「あんなとこで眠るなんて、自殺行為だぞ。あそこは丁度この基地に近かったからよかったけどな。」
男はそういうとマリアの傍らにしゃがみ込んだ。
「ちょっと傷を見せて…うーん…よかった、これならすぐにうごけるようになるだろう、本当に発見が早くてよかったよ。どこか痛いところはないか?」
「…ここは…どこ?」
まだよく状況がわかっていないマリアはただ首を横に振って言った。
「ここはおれたち革命軍のアジトの一つさ。丁度野営地から戻る途中で君を見つけてね。ここに連れてきたってわけだ。」
「革命軍…」
マリアも収容所で話には聞いたことがあった。いくつもの流刑地を抜けだし、この不条理な国を変えようとしている人々のことを。
「君も流刑地に居たんだな。まだ小さいのに…辛かっただろう。君の両親も一緒に逃げたのかい?」
「とうさまも、かあさまも収容所で死んだ。」
「じゃあ、君は一人で収容所から逃げてきたのか?」
彼は驚いたように目を見張った。
「そうか…しかし…君のような小さな子が一人で生きていけるような場所は今のこの国にはないよ…残念ながらね…」
「…でもどうしてもあそこにはいたくなかった。…あそこには悲しい想い出が多すぎるから…」
「そうか…まあ、しばらくはここにいるといい。傷が治るまでにはまだ時間がかかるからね。今、何か暖かいものを持ってくるよ、お腹がすいてるだろ。」
彼は微笑んで立ち上ろうとしたその上着の裾をマリアは思わずつかんでいた。どうしてそんなことをしたのかマリア自身わからなかった。彼は一瞬困ったような表情をしたが、すぐに微笑んで、マリアの手をはずすと、その手をそっと握ってくれた。
「大丈夫、すぐに戻るよ…えっと…君の名前は?」
「マリア…マリア・タチバナ……」
「マリアかいい名前だ。俺の名はユーリーだ、ちょっとまっててくれ、マリア。すぐ戻るから。」
ユーリーはそう言うと、部屋を出ていった。
一人になったマリアはそっと自分の手を見つめていた。丁寧に包帯の巻かれた両手にはまだユーリーの手のぬくもりが残っているかのようだ。
「…ユーリー……」
彼の名をつぶやきながらマリアは再び安心感からだろうか、眠気に襲われた。すぐに戻るというユーリーを待っていようと思いながらそのままずるずると眠りに落ちていった。
しばらくしてユーリーは一人の女性を連れて戻ってきた。
「あら…」
女性はマリアが寝ているのを見つけると微笑んだ。
「なんだ…また寝ちまったのか…」
「疲れてたのね…まだこんなに小さいのに一人で流刑地を飛び出して…」
「そうだな…この子が安心して暮らせる国にここを変えなくては…」
「そうね…」
二人はそのままマリアを起こさぬようにそっと部屋を出ていった。
マリアは懐かしいスープの香りに目を覚ました。
「あら、おはよ。よく眠ってたわね。」
そこにいたのはユーリーではなく見知らぬ女性だった。マリアは思わず壁に身を寄せ相手をにらみつけた。
「誰?」
「ごめんなさい、脅かしちゃったかしら。私はユーリーの同志、オルガよ。よろしくね。マリア」
「…………」
「あなたはどこの流刑地にいたの?」
「……シュシェンスコエ……」
「まあ、あんな遠くからここまできたのね…色々辛いことがあっただろうけど…ここにはあなたの仲間がたくさんいるわ、もう安心していいのよ。」
「…仲間?」
「ええ、ここでは同志と呼ぶけど、みんなあなたと同じ流刑地を飛び出してこの国を変えようとしているの。あなたのような子供たちが安心して暮らせる国にするために、がんばっているのよ。」
熱っぽく話すオルガの瞳からマリアはいつしか目が離せなくなっていた。今までマリアがみたことのないような希望に満ちて光り輝いているその青い瞳から。
「さあ、お腹がすいたでしょ。スープを持ってきたのよ。一緒に食べましょう。」
オルガはアルマイトの皿を差しだそうとしてマリアの両手が包帯でぐるぐる巻きになっていることを思いだした。
「その手じゃ、まだ一人で食事をとるのは無理ね。」
オルガはマリアをそっと起きあがらせると自分の腕の中にもたれかからせ、一匙とると息をかけてさましてやってから食べさせた。
「…美味しい……」
マリアの口元から思わず笑みがもれた。
「そう、よかった。このスープならいくらでもおかわりがあるから、どんどん食べてね。」
暖かいスープにマリアの凍えた心も少しずつ溶けていくようで、はじめはこわばっていた身体も次第に自然にオルガにゆだねられていった。
気がつくとマリアはオルガの分までスープを平らげていた。
「ごめんなさい…あなたの分のまで……」
「いいのよ、さっきも言ったけどこのスープは誰がいつ帰ってきてもいいようにいつでも作ってあるの、私はあとで食べてくるから。それより、マリアがこんなに食べてくれたことの方が私はうれしいわ。」
オルガの言葉にマリアは恥ずかしそうにうつむくと、小さな声で言った。
「ありがとう…こんなに美味しいスープ飲んだのは久しぶりだった…」
マリアの身体をそっと抱きしめることでオルガはその言葉に応えた。