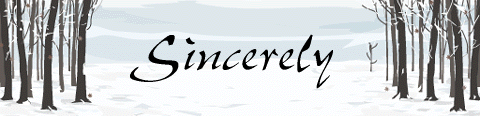
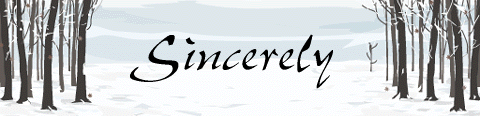
オルガの献身的な介護でマリアは少しずつ回復していった。しかし、凍傷でまだ満足に歩けないため一日のほとんどを部屋の中で過ごしていた。わかったことはここがオルガの部屋であるということぐらい。通路から話し声は聞こえてくるが実際に顔を合わせているのはオルガだけだった。
ある日、ユーリーがオルガとともにやってきた。この日の二人はは同じカーキ色の戦闘服を着ていて、オルガは少し癖のある髪を後ろで無造作に一つに束ねていた。
「マリア、調子はどうだい?」
「…だいぶ…痛みはひいてきた……」
「そうか、よかった。オルガはやさしくしてくれるかい?」
「うん。」
「そうか…政府軍も恐れる「クワッサリー」のオルガもマリアには優しいか。」
ユーリーはそう言って笑ったが意味がわからないマリアは目を白黒させていた。
「それは言いッこなしよ。マリアがびっくりしてるじゃないの。」
「…くわっさりー?」
「ああ、「クワッサリー」…火喰い鳥。こうみえても、オルガは我々同志の中でも屈強の戦士の一人なんだ。」
マリアはますます驚いた。マリアの知っているオルガは優しい女性で、屈強の女戦士というユーリーの言葉とはどうにも一緒にならなかったからだ。
「そうなの?」
不思議そうにマリアが振り返って尋ねると、オルガはちょっと困った顔をした。
「ええ、誰がつけたかしらないけど…クワッサリー…火喰い鳥なんて呼ばれてるわね。」
「戦場でのオルガは俺たち男も真っ青な勇敢な戦士なのさ。」
「そうなの?…とてもそんな風には見えない…けど……」
「ああ、そうさ。俺もオルガには何度も助けてもらったぐらいだ。」
「あら、ユーリーにはその倍は助けてもらったわよ。」
顔を見合わせて笑い合う二人をマリアもつられて微笑んだ。
ある夜、オルガは小さなうめき声で目を覚ました。
「傷が痛む?」
マリアは首を振って、小さく答える。
「…寒い……」
その答えにオルガは黙って隣の寝床に潜り込んで小さな身体をそっと抱きしめた。
「今夜は一緒に寝ましょう。」
答える代わりにマリアはオルガに身体を預けてきた。
「あったかい……」
「私も、こうしていると暖かい…なんだか懐かしい感じ。」
「昔…吹雪が怖かったの…怖くて泣いてると、かあさまのベッドに潜り込んでた。」
「そう……私もね、そうだったわ。」
「オルガも?」
「ええ。私とユーリーは同じ村の出身なの…シュシェンスコエよりももっと北の海に近い小さな村でね。私の父親は戦争に反対してそれでその流刑地に送られたの。昔はペテルスブルグに住んでいたから、慣れないことばかりだった。吹雪の夜には風の音に混じってゴーーッと波の音が聞こえてくるの。それがまるで何かの怪物の鳴き声みたいで怖くて。よく泣いてた。そうすると母がいつもこんな風に添い寝してくれてね…信じられないでしょ?私にだってそんな可愛い頃があったのよ。」
屈強の革命戦士だというオルガの告白にマリアは思わず笑みを漏らした。
「あら、笑ったわね。私だって小さい時はあったんだから。…とにかく、そこで私たちは細々と暮らしていた。そんな時、ペテルスブルグに残っていた叔父から手紙が来たの。そのころ戦争は敗色が濃厚で労働者たちの生活は最悪だった…それで、いよいよ労働者が蜂起するから父親にも流刑地を出て合流して欲しいという知らせだったわ。」
淡々と語るオルガの顔をマリアは黙って見つめていた。
「そして父は家族を残して流刑地を脱出してペテルスブルグの労働者運動に参加するようになった。そしてあの日「血の日曜日」事件。軍隊の発砲で叔父は死に、父は重傷を負って2ヶ月後にその傷がもとで死んだわ。表向き革命は成功したようだったけれど実際は何も変わらなかった。そんな状況で新たな革命軍を募る人たちが流刑地にやってきた。この国を変えよう…その希望に満ちた瞳を信じてユーリーと私は革命軍に参加した。そして、今もこの国を変えるために私たちは活動しているのよ。」
マリアを抱きしめる腕に力がこもる。
「オルガは今でも吹雪が怖い?」
「そうねぇ…今でも夢に見ることがあるわ。あの北の海の怪物の叫び声を。」
「じゃあオルガが怖いときはマリアが抱きしめてあげる。」
「マリア…ありがとう。」
オルガは自分の胸の中の少女の髪口づけた。
少しずつ動けるようになると、マリアは基地の中の賄いを手伝うようになった。小さな子供がかいがいしく働く姿は戦いに疲れた革命軍の兵士たちにとっても安らぎの一つになったらしく、いつの間にかマリアは基地の中のアイドルになっていた。
今日もマリアは「プロレタリアートよ団結せよ!」などという声の響く食堂の中をかけまわり笑顔を振りまいていた。
「マリアが来てからここもずいぶん雰囲気が変わったよなぁ。」
偵察任務から帰ったユーリーはそんなマリアの様子を見つめながら呟いた。
「そうね…マリアもすっかり元気になって……」
「どうした?オルガ。浮かない顔をして。」
「ええ…マリアはここにいるのが幸せなのかしら…マリアにとってここは危険な場所だと思うの。」
髭面の兵士達と談笑するマリアを見ながら、オルガの顔に困惑の色が浮かんだ。
「…確かに…そうかもしれないな。しかし、俺達はマリアに恥じるようなことはしていないぞ。」
「それはもちろんよ。私は誇りをもって革命軍に入ったわ。でもマリアは違う。マリアは自分で選んでここに来たわけではないわ。マリアの将来は彼女のものだもの。」
「しかし、聞いたところだとあの子の母親は日本人だというじゃないか。それが元で家族で流刑されたんだろう。そんなあの子を世話してくれる人がいるだろうか。」
「それなら当てがあるの。」
オルガは身を乗り出すように切り出した。
「私の母方の叔母がこの先の町に住んでるの。もちろん私が革命軍に入っていることは知ってるわ。叔父が「血の日曜日」で死んでからはずっと独り者で子供もいないの。叔母ならきっとマリアを育ててくれると思うのよ。」
「なるほど…オルガのことも認めてくれているのなら、大丈夫かもしれないな。それに幼いマリアが革命軍の内部を知っているなんて誰も思わないだろうし。」
「私、今度の偵察の時にでも一度叔母のところに行って頼んでみようと思うの、どうかしらユーリー。」
「そうだな。もし、君の叔母さんが承知してくれたらきっとマリアにはその方がいいに違いない。でも、マリアにはどう伝える?マリアはずいぶん君になついてるようだが…」
ユーリーの言葉にオルガはちょっと淋しげに微笑んだ。
「ええ。私もマリアがかわいいわ。ずっと一緒にいられたらどんなにいいか…でもそれではマリアのためにならないもの…マリアには叔母さんの承諾が得られたら私から話すわ。」
「そうだな…それがいい、オルガの叔母さんのところだと言えばマリアもイヤとは言わないだろう。」
「ええ…」
オルガは小さく頷いた。
「あ、オルガ、ユーリー。お帰りなさい。」
そんな二人を見つけたマリアが走ってくる。
「ただいま、マリア。すっかりみんなと仲良くなったみたいだね。」
「うん。今日はね、スープを作るのもお手伝いしたの。」
「あら、マリアの作ったスープなのね。」
オルガの言葉にマリアはちょっと恥ずかしそうに頬を染めて俯いた。
「うん…タマネギの皮をむいて、お鍋をかき回してだけだけど…」
「そうか、じゃあ、心して食べなきゃな、オルガ。」
「そうね、マリアの作ったスープだもの。」
「じゃあ、今持ってくるね、そこのテーブルに座って待っててね。」
マリアはそういうとトコトコと厨房の奥に駆け込んでいった。
そんなマリアを見ながら、オルガは決意したように小さく頷いた。
数日後……。
「今日は一緒に寝ましょう。」
オルガに言われてマリアは何か言いようのない不安に襲われた。
ここに来た当初は一緒に寝ていたが、ユーリーがマリア用の寝床を作ってくれてからはいつもそこで寝るように言われていた。もちろん、二人で寝たことがないわけではない。しかし、いつでもそれはマリアから言い出したことでオルガから言ってくるようなことはなかったのである。
「…どうして?オルガ、どうして突然そんなこと言うの。」
マリアは時々このように勘の鋭いところを見せた。ここに来て以来外に出たことはまだないにも関わらず、しばしば天気を当てて見せたりするのだ。
「あなたに隠し事をしてもだめみたいね。今日はゆっくりと話したいことがあるの。だから、ね。」
オルガの言葉にマリアは小さく頷いて、一緒に寝床に潜り込んだ。
「マリア…元気になったわね…本当にうれしい…」
優しく髪を撫でられながら、マリアはただオルガを見つめていた。
「もうそろそろ、ここを出た方がいいと思うの。」
「どうして? 私、ここが好き、みんなが好き。ここにいたい。」
マリアの真摯な叫びにオルガは小さく首を横に振った。
「私もマリアとずっと一緒にいたいわ…でもね、ここはあなたのような幼い子がいるところではないのよ。ここにいるとわからないかもしれないけど、私たちはこの国を相手に戦争をしているの、ここもいつ危険な場所になるかわからない。そんなところにいつまでもあなたをおいておくことはできないわ。」
マリアはただ呆然とオルガの顔を見つめている。
「この少し先の町に、私の叔母が住んでるの。叔父はすでに亡くなって、今は一人暮らしなんだけど、そこでマリアを預かってくれるっていうのよ。」
「……………」
「今回の偵察の帰りに叔母に会ってきたの。叔母は子供もいないから、マリアのことを話したらすごく喜んでくれたわ。」
「オルガは…その方がいいと思う?」
「ええ。叔母のところなら、この革命が成功した後、すぐにマリアに会いにいけるでしょ?」
「…革命が成功したら……会いに来てくれるの?また一緒に暮らせるの?」
「ええ。もちろんよ。マリア、あなたは私にとってももうかけがえのない家族だもの。必ず迎えに行くわ。だから…ね。」
「………オルガが行けっていうなら……迎えに来てくれるなら………」
マリアはそれだけ言うとオルガの胸に顔を埋めてしまった。オルガは自分の胸元が濡れていくのを感じていていた。
「…マリア……」
オルガの瞳からも涙が一筋流れた。
「そうか…マリアは承知したか。」
オルガの報告にユーリーは言葉少なにそう言うと、オルガの肩をそっと抱いた。
「ええ。あの子は賢い子だから…ちゃんと話したらわかってくれたわ…」
真っ赤になった目でオルガは力無く言った。
「しかたがない…それがマリアにとっては一番いいことなんだから。俺達はマリアが安心して暮らせる国を早く作るんだ。」
「そうね…そうよね……」
オルガは自分を納得させるように何度もそう呟いていた。
「いつ…連れて行くんだ?」
「そうね…とりあえず明日の偵察の時にもう一度叔母のところへいってくるわ。そうしたらなるべく早く…」
「わかった。気をつけてな。」
「ええ。」
次の日の朝早く、オルガは偵察にでかけるために準備をしていた。小隊を率いてのいつもの偵察なので特にマリアを起こすこともなく出かけるはずだった。
しかし、マリアは起きていた。
「マリア…ごめんなさい、起こしちゃったかしら。」
「……オルガ…偵察にいくの?」
「ええ。ついでに叔母のところにも寄って改めてマリアのことを頼んでくるわ。」
努めて笑顔で言うオルガの袖口をマリアがクッと握りしめた。
「どうしたの?」
「行かないで。」
「え?」
「行かないで…行っちゃだめ!」
そう叫ぶとマリアはオルガに取りすがった。
「マリア…この前も話したでしょ。…しかたないのよ。」
「違うの…違うの…そんなのじゃないの…なんだかわかんないけど…オルガ、今日は行っちゃだめ。」
「マリア…そんなわがまま言わないで、私だってマリアとずっと一緒にいたいけど…そういうわけにはいかないのよ。ね、わかってちょうだい。」
叔母のところに会いに行けば本当に自分がここから離れなければならないからマリアがそんなことを言って駄々をこねているのだとオルガは思っていた。このままズルズルと出発を遅らせてはマリアにとっても自分にとってもかえって辛くなる。オルガはそっとマリアを引き剥がした。
「いい子でお留守番していてね。」
「…オルガ……」
オルガは振り返らずに部屋を出ていった。
「…オルガ…だめ…行っちゃだめ……。どうしてかわからないけど…とにかく行っちゃだめなのに……」
一人残された部屋の中でマリアはいつまでも泣いていた。
不安に一人毛布にくるまって震えていたマリアの元にユーリーがやってきたのはもう夜になってからのことだった。
「マリア!ここにいたのか。」
「ユーリー…」
「マリア…泣いていたのか…誰かがもう知らせにきたのか?」
「なんのこと?」
「知らないのか?」
「わからない…なにもしらない…ただ、なんだか怖くて悲しくて…」
「…マリア……君にはもしかしたら僕らにはない不思議な力があるのかもしれないな…」
首を傾げるマリアをユーリーはそっと抱きしめてゆっくりと語りかけるように話し始めた。
「いいかい、マリア。気を落ち着けて聞くんだよ。」
マリアが小さく頷くのを確認してからユーリーは続けた。
「オルガが死んだ。彼女の叔母さんも一緒だ。」
マリアは驚きに大きく瞳を見開いた。
「どうやら叔母さんの隣人の中に憲兵に密告した奴がいたらしい。待ち伏せされていたんだ。」
「オルガ…オルガ………」
マリアはユーリーにしがみつくようにして声をあげて泣いた。
「オルガは…どこにいるの?」
「……オルガの遺体は憲兵が村の広場に晒しているという話だ。俺達をおびきだすためにな。」
「…ひどい…オルガ…かわいそう……」
マリアはあまりのことに唇をかみしめた。
「それで憲兵達がこの基地を探すために山狩りを始めようとしているらしい。俺達はこの基地を捨てる。マリア、君はまだ小さいから奴らも下手に手はだしてこないだろう。一人で麓の村まで先に逃げるんだ。」
「イヤ、私も行く。」
「マリア…でもね、これは危険な移動になる…君はまだ怪我が治ったばかりだし…」
「絶対に足手まといにはならない。きっとユーリー達の役に立つ。私みたいな子なら目立たないって今、ユーリーが言ったのよ。だったらそんな私が役立つはず。」
「マリア………」
「お願い…私、戦いたいの。私のとうさまやかあさまや…今度はオルガまで…本当はずっと考えてた。でも私はまだ小さいからだめだと思ってた…。でも私にもできことがあるはず。だから、お願い。ユーリー。」
マリアはもう泣いてはいなかった。かわりにその緑色の瞳が燃えるように輝いていた。
「…わかった。しかし、今度の旅は辛いぞ。」
ユーリーの言葉にマリアは力強く頷いた。
幼い革命戦士、マリア・タチバナの誕生だった。
Ende
<番頭・彩の言い訳>
というわけで少女マリア第2弾でございます。
とにかく一番引っかかっていた「マリアはなぜ革命軍に入ったのか」と
いうところを書いてみようと思ったのはいいんですが、とにかくロシア革命についての
知識が皆無で、その勉強から初めてしまいまして、すっかり遅くなってしまいました。
おまけにオリキャラがかなり出て来ちゃってますしねぇ(苦笑)
文体も二転三転して、やっと今の形に落ち着きました(^_^;)
まだまだ力不足の感はありますが、楽しんでいただければと思います。
尚、この場を借りまして…袋小路に迷い込んで困ってるとこで助言をくれた
Noahちゃん、ろざ番頭、そして母(笑)ありがとう。またお世話かけるとおもいますが、よろしく(笑)。